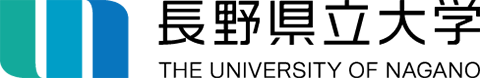参加学生の声
※研修先および研修内容は実施年度により異なります。
グローバルマネジメント学部グローバルマネジメント学科
| 研修先 | イギリス・レスター レスター大学 |

海外の魅力に触れ、次はどこへ行こうかとワクワクしています
※2023年度実施
長野県岩村田高等学校出身 小泉日菜さん
長野県岩村田高等学校出身 小泉日菜さん
プログラムの一環として、レスターシティーFCのホームスタジアムを訪れ、マネジメントについて実際に施設を見ながら学習をする機会がありました。普段は入れない選手ルームやインタビュールームなどにも入ることができ、思い出深いものとなりました。また、実際に生活の中で当たり前のように英語を話す機会を得られたことで、より自分自身の英語学習への意欲が向上し、海外での経験が自分を成長させてくれたことを実感しました。


| 研修先 | ニュージーランド・クライストチャーチ ニュージーランド国立工科大学(現:AICクライストチャーチ工科大学) |

温かなホストファミリーの支えで英語で思いが伝えられるように
※2023年度実施
静岡県立掛川東高等学校出身 山中 大空さん
静岡県立掛川東高等学校出身 山中 大空さん
初めての海外は不安も大きかったですが、ホストファミリーの優しさに常に支えられていました。心に残る学びとしては、ニュージーランドでの1週目にアウトドアブランドKathmanduを訪問し店舗展開やグローバル展開について伺ったこと。2週目には海岸沿いの温泉施設He Puna Taimoana(マオリ語で「海辺のプール」という意味)で、経営戦略を伺ったことです。その成果は英語でのプレゼンテーションに結実しました。



鍛えたはずのリスニングカが通じない?!
困難にぶつかって得たものは、積極性と視野の広がり。
困難にぶつかって得たものは、積極性と視野の広がり。
※2023年度実施
長野県大町岳腸高等学校出身 佐野怜香さん
長野県大町岳腸高等学校出身 佐野怜香さん
2年次に学科全員でニュージーランド(以降NZ)へ研修に行きました。午前中は少人数クラスで英語授業、午後は専門授業で、現地では驚きと戸惑いの連続でした。リスニングにはやや自信があったのですが、当初はオセアニア訛りがある上に、全体的にかなり早口に感じました。'friend'や‘eight'といった基本的な単語も訛って話されると聞き取れず、とても不安でした。その一方で、滞在はホームステイだったので、受け入れ先のお母さんにはとても助けられました。料理好きな方で、私が栄養について勉強していると知ると、調理やレシピの説明をしてくれたり、日本食のお弁当を作ってくれたり、戸惑いの多い2週間でしたが、温かく接していただき、とてもお世話になり感謝しています。本研修は私にとって初めての海外経験でしたが、英語だけの環境で揉まれたことで、英語でのコミュニケーションに抵抗はなくなりました。帰国後日本で、電車で困っている外国の方に自分から声をかけるほど積極的になりました。日本とは異なる生活習慣に触れ、NZの管理栄養士制度を知ったことは、私の視野を広げてくれました。現在の勉強のモチベーションにもつながっており、私は海外研修で確かに成長できたと感じています。


健康発達学部こども学科
| 研修先 | フィンランド・ヘルシンキ ヘルシンキ大学等 |

子どもの「もっと知りたい」、「やってみたい」を大切にした保育
※2023年度実施
長野県松本県ケ丘高等学校出身 高柳 梓さん
長野県松本県ケ丘高等学校出身 高柳 梓さん
フィンランドの保育は、「大人になったときにどんな人問になってもらいたいか」を軸に、子どもたちが経験を通して自分で考え学んでいくことに重きを置いています。保育者は安全に配慮しつつ、子どもたちの様子を見守りながら、時には問いを投げかけるなど、興味の芽を一緒に育む姿がありました。どんな天気でも様々な学びのチャンスと捉え、寒くても、雨が降っていても森へ向かい、そこで遊ぶ子どもたちに豊かさを感じました。



日本とは異なる幼児保育に接し
保育者の役割を強く意識することに。
保育者の役割を強く意識することに。
※2022年度実施
函館市立函館高等学校出身 吉武マリアエリカさん
函館市立函館高等学校出身 吉武マリアエリカさん
研修先では、フィンランドの幼児教育や保育制度について学びました。授業は英語か、現地の先生がフィンランド語で説明するのを、その場で県立大学の先生が日本語に訳す形でした。ヘルシンキ大学のボランティアサークルの学生が彼らの活動について説明してくれることもありました。保育所での実習もあります。フィンランドが力を入れている「就学前教育」では、6歳の子が、与えられたテーマについて家族と話し、それを母国語ではない英語で発表していて驚きました。また「転びながら転び方を学ぶ」という言葉があるそうですが、最低限の安全には配慮しつつも、できるだけ大人は介入せず、子ども同士の関わりへの理解を大切にしている「見守り保育」も印象的で、幼児教育に対する考え方や、保育者のあるべき姿が広がりました。「世界中の子どもを見てみたい」というのが夢だったので、フィンランドの子どもたちと通じ合えた時はとても感動したのですが、ヘルシンキ大学で話した学生の、幼児教育を通して社会を変えたいという志の高さにも、大変感銘を受けました。自分もいずれは保育を通して社会を作ることになるのだという意識を強く持てるようになったのは、この研修の賜物です。