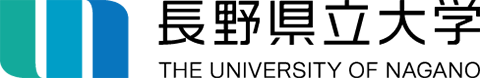「保育研究者」と「園長先生」、ダブルワークの過去も。太田教授が考える子も親も先生も幸せな保育のあり方とその実践とは? 健康発達学部長 太田 光洋 教授
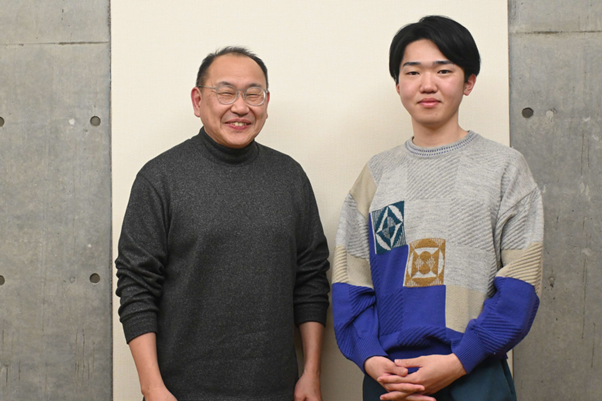
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
長野県立大学が目指すソーシャルイノベーションのためには、理論と実践の両方が欠かせません。そしてこの大学には、地域の中に溶け込んでいくフィールドリサーチとそこから得た知見を地域に還元していく実践の両方に取り組む個性豊かな教員たちが数多くいます。
その一方で、大学の教員がどんなことを考え、どんな思いで研究に取り組んでいるのかが見えづらいのも事実です。
そこで教員たちに最も近い、長野県立大学の学生が、各学部学科、研究科の教員にインタビューを行い、研究されていることや地域との連携について、お話をお伺いしました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「保育」と聞いて、あなたはどのようなことをイメージしますか?
昨今、共働きの親が増える一方で、保育園が足りないといった「待機児童問題」が報じられたり、ワンオペ育児のような「孤育て」が話題になるなど、様々な課題が取り巻く保育。
ともすると、いかに効率的に保育を行うかが話題の中心になってしまいますが、本来子育てとは楽しく尊い営みでもあります。そんな保育や子育ての原点を思い出させてくれたのが、保育学を研究され、健康発達学部長でもある太田 光洋教授です。
太田教授が、幼児教育に目覚めたきっかけや、子も親も保育園の先生も楽しく幸せな子育てに向けて取り組んでいる研究や地域での実践についてお話を伺いました。
インタビュー日:2025年1月16日
聞き手・書き手:内田 大晴(長野県立大学グローバルマネジメント学部2年 学生コーディネーター)
写真・編集:北埜 航太(長野県立大学 ソーシャル・イノベーション創出センター 地域コーディネーター)
長野県立大学が目指すソーシャルイノベーションのためには、理論と実践の両方が欠かせません。そしてこの大学には、地域の中に溶け込んでいくフィールドリサーチとそこから得た知見を地域に還元していく実践の両方に取り組む個性豊かな教員たちが数多くいます。
その一方で、大学の教員がどんなことを考え、どんな思いで研究に取り組んでいるのかが見えづらいのも事実です。
そこで教員たちに最も近い、長野県立大学の学生が、各学部学科、研究科の教員にインタビューを行い、研究されていることや地域との連携について、お話をお伺いしました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「保育」と聞いて、あなたはどのようなことをイメージしますか?
昨今、共働きの親が増える一方で、保育園が足りないといった「待機児童問題」が報じられたり、ワンオペ育児のような「孤育て」が話題になるなど、様々な課題が取り巻く保育。
ともすると、いかに効率的に保育を行うかが話題の中心になってしまいますが、本来子育てとは楽しく尊い営みでもあります。そんな保育や子育ての原点を思い出させてくれたのが、保育学を研究され、健康発達学部長でもある太田 光洋教授です。
太田教授が、幼児教育に目覚めたきっかけや、子も親も保育園の先生も楽しく幸せな子育てに向けて取り組んでいる研究や地域での実践についてお話を伺いました。
インタビュー日:2025年1月16日
聞き手・書き手:内田 大晴(長野県立大学グローバルマネジメント学部2年 学生コーディネーター)
写真・編集:北埜 航太(長野県立大学 ソーシャル・イノベーション創出センター 地域コーディネーター)

プロフィール:宮城教育大学教育学部を卒業後、同大学院やシンガポール国立大学の客員研究員、旭川大学附属幼稚園園長など研究と現場の両方を経験する。2018年より長野県立大学健康発達学部こども学科教授。また、長野県教育委員会の信州幼児教育支援センター長、日本保育文化学会の会長なども務める。一貫して、保育の現場に寄り添いながら、子どもの自然な発育や、親が楽しく子育てするための支援、親や子に接する保育士の幸福な働き方など、保育に関わる人全ての幸福を考えた研究や提言を行う。
「遊び」が「学び」に。太田先生が思う幼児教育の面白さ
ーー太田先生が保育の道に進んだきっかけを教えてください
きっかけは、大学で入ったサークルですね。当時、「セツルメント」という活動があり、毎週土曜日に学生たちが特定の地域の公園に集まり、幼児・小学生・中高生のグループを作って交流していました。幼児は近所の家を回って声をかけ、預かる形で関わり、小学生は遊び、中高生は勉強をしたりしていました。
ーー幼児教育だけでなく小学生や中高生の教育にもかかわっていたのですね
はい。むしろ私はもともと小学生に興味があったのですが、当時サークル内で幼児を担当する学生がいなかったため、「誰かやらないか?」と言われ、特に深く考えずに引き受けたのが最初で、そこから幼児教育に関心を持つようになりました。
ーーサークル活動がきっかけで最終的に幼児教育の研究者になったというのは驚きです。幼児教育のどういうところに魅かれたんですか?
幼稚園は小学校とは違って国語とか算数みたいに教えることが決まっていないので、ガイドラインはあるものの教えることの大部分が先生の創意工夫にかなり委ねられます。その自由さにまず面白味を感じました。また、幼児は勉強をするわけではないのに、遊びの中ですくすくと育っていくところがおもしろいなと感じました。遊びは誰からも強制されないし目的がない。遊ぶこと自体が楽しいからやっているんだけど、やっているうちに自然といろいろな力が身についてしまう。例えば砂場遊びやままごとで、夢中になって自分の遊びを広げていくと他の子の遊びに干渉してトラブルが起きてしまったり、「こういう遊びをしたい」というイメージを持ちながらも、一人では実現できないことがあります。そんなときに、どうすれば友達を巻き込めるのか、相手と折り合いをつけながら遊びを発展させていく力が育まれていくのです。そういうところが非常に面白いなと思ってこの道に進みました。
きっかけは、大学で入ったサークルですね。当時、「セツルメント」という活動があり、毎週土曜日に学生たちが特定の地域の公園に集まり、幼児・小学生・中高生のグループを作って交流していました。幼児は近所の家を回って声をかけ、預かる形で関わり、小学生は遊び、中高生は勉強をしたりしていました。
ーー幼児教育だけでなく小学生や中高生の教育にもかかわっていたのですね
はい。むしろ私はもともと小学生に興味があったのですが、当時サークル内で幼児を担当する学生がいなかったため、「誰かやらないか?」と言われ、特に深く考えずに引き受けたのが最初で、そこから幼児教育に関心を持つようになりました。
ーーサークル活動がきっかけで最終的に幼児教育の研究者になったというのは驚きです。幼児教育のどういうところに魅かれたんですか?
幼稚園は小学校とは違って国語とか算数みたいに教えることが決まっていないので、ガイドラインはあるものの教えることの大部分が先生の創意工夫にかなり委ねられます。その自由さにまず面白味を感じました。また、幼児は勉強をするわけではないのに、遊びの中ですくすくと育っていくところがおもしろいなと感じました。遊びは誰からも強制されないし目的がない。遊ぶこと自体が楽しいからやっているんだけど、やっているうちに自然といろいろな力が身についてしまう。例えば砂場遊びやままごとで、夢中になって自分の遊びを広げていくと他の子の遊びに干渉してトラブルが起きてしまったり、「こういう遊びをしたい」というイメージを持ちながらも、一人では実現できないことがあります。そんなときに、どうすれば友達を巻き込めるのか、相手と折り合いをつけながら遊びを発展させていく力が育まれていくのです。そういうところが非常に面白いなと思ってこの道に進みました。

研究」と「現場」、二足のわらじ
ーー「遊び」が「学び」になるというのは非常に面白いですね。そこで保育士ではなく研究者になったのはなぜですか?
卒業論文を担当してくださった先生が、私の卒論を評価してくれて「保育現場のことを深く理解している研究者がほとんどいない。だから君は実践実務を理解した研究者になりなさい」と言われたんです。それで4年現場で働いた後に、大学院に進学しました。大学院の1年目で単位を取得し、2年目は昼間に保育現場で仕事をしながら家に帰ってきてから研究をする生活をしていました。修士論文を執筆する形で学びました。
ーーまさに実践を通しての研究をされていたんですね。
そうですね。その後旭川大学の短大の幼児教育学科学部に赴任した際にも、偶然にも付属幼稚園の幼稚園長を任されまして。その時は、幼稚園保育園経営と大学での研究、現場と研究の二足のわらじでしたね。
ーー当時はどのような研究をされていたのですか?
主に子育て支援の研究をしていました。30年前くらいの話ですが、当時北海道には始まったばかりの子育て支援を実践している保育施設が5か所ありまして、その一つが関わりのあった保育園でした。そこで、その園の方から「子育て支援を取り入れたいから協力してくれないか」と依頼されて、研修をしたり実践を理論化していくことを行いました。そのうち他の施設の方からも呼ばれるようになり、多い年は1年間で100回近い研修を行っていました。
ーー子育て支援が始まったのは意外と最近なんですね
もともと子育て支援は少子化対策の文脈で始まった取り組みなので、時期としては30年前ぐらいからですね。今の時代、親になるということについての学びが基本的にあまりないまま大人になっているので、例えば子どもを持ったときに、わからないこととか、困ることはたくさんあるわけですよね。そういう親子が、最初に通うところが保育園なので、どういうふうに子育てをすれば良いか、どんな子育てならやりやすいかを、親御さんにも学んでもらえるような支援をしていくのも子育て支援です。
卒業論文を担当してくださった先生が、私の卒論を評価してくれて「保育現場のことを深く理解している研究者がほとんどいない。だから君は実践実務を理解した研究者になりなさい」と言われたんです。それで4年現場で働いた後に、大学院に進学しました。大学院の1年目で単位を取得し、2年目は昼間に保育現場で仕事をしながら家に帰ってきてから研究をする生活をしていました。修士論文を執筆する形で学びました。
ーーまさに実践を通しての研究をされていたんですね。
そうですね。その後旭川大学の短大の幼児教育学科学部に赴任した際にも、偶然にも付属幼稚園の幼稚園長を任されまして。その時は、幼稚園保育園経営と大学での研究、現場と研究の二足のわらじでしたね。
ーー当時はどのような研究をされていたのですか?
主に子育て支援の研究をしていました。30年前くらいの話ですが、当時北海道には始まったばかりの子育て支援を実践している保育施設が5か所ありまして、その一つが関わりのあった保育園でした。そこで、その園の方から「子育て支援を取り入れたいから協力してくれないか」と依頼されて、研修をしたり実践を理論化していくことを行いました。そのうち他の施設の方からも呼ばれるようになり、多い年は1年間で100回近い研修を行っていました。
ーー子育て支援が始まったのは意外と最近なんですね
もともと子育て支援は少子化対策の文脈で始まった取り組みなので、時期としては30年前ぐらいからですね。今の時代、親になるということについての学びが基本的にあまりないまま大人になっているので、例えば子どもを持ったときに、わからないこととか、困ることはたくさんあるわけですよね。そういう親子が、最初に通うところが保育園なので、どういうふうに子育てをすれば良いか、どんな子育てならやりやすいかを、親御さんにも学んでもらえるような支援をしていくのも子育て支援です。
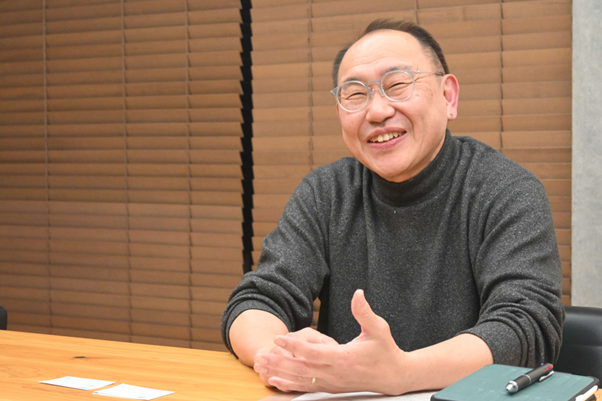
大学を飛び出し、ゼミ生とともに保育の最前線へ
ーー太田先生は、長野県立大学に来てからはどんなことに取り組んでいますか?
いろいろやっていますが、主に長野県の教育委員会が運営する“信州幼児教育支援センター”のセンター長を務めています。そこでは、県内の保育園、幼稚園、こども園などの研修やさまざまな取り組みを進めていて、県全体の保育に関わる仕事をしています。もう一方で、地域ごとにニーズがあれば現地に行って、継続子育て支援や小学校への接続に関する活動も行っていますね。
ーー大学としての取り組みもご紹介いただけますか?
そうですね。大学としては地域貢献サークル 「ぐるんぱ」の活動を立ち上げました。これは、1期生の学生たちと「地域の支援をやってみない?」と話したのがきっかけで始まりました。今ではこども学科の半数以上の学生が参加しています。それから、飯綱町と保育の連携協定を結んでいて、月に2回ほど学生が飯綱の子育て支援センターに行ってサポート活動をしています。毎回8人くらいの学生が参加していて、飯綱町がバスで迎えに来てくれるんですよ。
ーーひとり親家庭の支援もされているとか。
はい、「ぐるんぱ」を中心にNPOと提携して学生たちがひとり親家庭の支援も行っています。月に2回大学で企業や個人から集めた寄付をひとり親家庭に届ける活動ですね。新学期には学用品、現金寄付で購入したもの、あるいはお米のように現物寄付されたものも配布しています。
さらに、月に1回、土曜日に“ひとり親家庭の親子が遊びに来られる場”を作って、支援活動をしています。
教員が中心で動くのではなく、学生が取り組むさまざまな活動を支援するのが大切だと考えています。
ーーゼミ単位でも実践の場があるんですね。
はい。たとえば、飯綱の保育園に行って子どもたちと一緒に木で家作りをしたり、先生たちの研修会に学生も参加させてもらったりしています。現場で学ぶ機会を大事にしていて、学生たちもすごく意欲的に取り組んでいますね。
いろいろやっていますが、主に長野県の教育委員会が運営する“信州幼児教育支援センター”のセンター長を務めています。そこでは、県内の保育園、幼稚園、こども園などの研修やさまざまな取り組みを進めていて、県全体の保育に関わる仕事をしています。もう一方で、地域ごとにニーズがあれば現地に行って、継続子育て支援や小学校への接続に関する活動も行っていますね。
ーー大学としての取り組みもご紹介いただけますか?
そうですね。大学としては地域貢献サークル 「ぐるんぱ」の活動を立ち上げました。これは、1期生の学生たちと「地域の支援をやってみない?」と話したのがきっかけで始まりました。今ではこども学科の半数以上の学生が参加しています。それから、飯綱町と保育の連携協定を結んでいて、月に2回ほど学生が飯綱の子育て支援センターに行ってサポート活動をしています。毎回8人くらいの学生が参加していて、飯綱町がバスで迎えに来てくれるんですよ。
ーーひとり親家庭の支援もされているとか。
はい、「ぐるんぱ」を中心にNPOと提携して学生たちがひとり親家庭の支援も行っています。月に2回大学で企業や個人から集めた寄付をひとり親家庭に届ける活動ですね。新学期には学用品、現金寄付で購入したもの、あるいはお米のように現物寄付されたものも配布しています。
さらに、月に1回、土曜日に“ひとり親家庭の親子が遊びに来られる場”を作って、支援活動をしています。
教員が中心で動くのではなく、学生が取り組むさまざまな活動を支援するのが大切だと考えています。
ーーゼミ単位でも実践の場があるんですね。
はい。たとえば、飯綱の保育園に行って子どもたちと一緒に木で家作りをしたり、先生たちの研修会に学生も参加させてもらったりしています。現場で学ぶ機会を大事にしていて、学生たちもすごく意欲的に取り組んでいますね。

ゼミ活動の様子
子育ては本当は楽しいもの。
原点回帰のための対話の場づくり
ーー太田先生は長い間、現場と研究を通して幼児教育に携わってこられたと思いますが、今の幼児教育の課題感はどのようなところにあると思いますか?
そうですね。子育て支援は少子化対策として始まったんだけど、労働力の確保とか、子育てにお金がかかることの経済的な支援みたいな観点だけじゃなくて、子どもにとってどういう親子関係がいいのかとか、そういう方向にもちゃんと目を向けることが大事だと思います。特に懸念しているのは、日本では保育所の保育時間が長すぎるんじゃないかということですね。親が自分で自分の子どもを育てる権利っていうのが、ちゃんと保障されてないというか。もちろん親が働くことも大事だし、それもいいと思うんだけど、もっと親が子どもと一緒にいられる時間を増やしてあげられないかと。ただ、子育てに時間をかけたいけれど、仕事ができない分、収入が減るっていう、仕事と子育てのバランスでうまくいってないところがあるなと思ってます。ある種の世の中の歪みが保育現場にしわ寄せとして出ているというのはあるかもしれません。
そうですね。子育て支援は少子化対策として始まったんだけど、労働力の確保とか、子育てにお金がかかることの経済的な支援みたいな観点だけじゃなくて、子どもにとってどういう親子関係がいいのかとか、そういう方向にもちゃんと目を向けることが大事だと思います。特に懸念しているのは、日本では保育所の保育時間が長すぎるんじゃないかということですね。親が自分で自分の子どもを育てる権利っていうのが、ちゃんと保障されてないというか。もちろん親が働くことも大事だし、それもいいと思うんだけど、もっと親が子どもと一緒にいられる時間を増やしてあげられないかと。ただ、子育てに時間をかけたいけれど、仕事ができない分、収入が減るっていう、仕事と子育てのバランスでうまくいってないところがあるなと思ってます。ある種の世の中の歪みが保育現場にしわ寄せとして出ているというのはあるかもしれません。
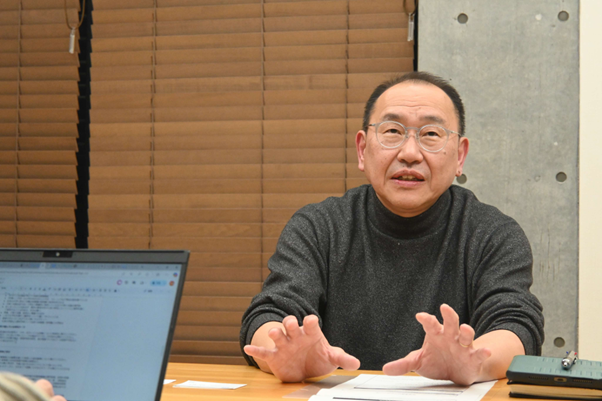
ーーそこをバランスをとっていくためにはどうしたらいいと思いますか?
なかなか難しい問題ですが、目の前のことばかり考えてると近視眼的になっちゃうので、本当はグランドデザインみたいなものを考えて、展望を持ってやっていくっていうのが必要だなと思います。話は広がりますが、これから子どもが減っていく中で、学校を子どもたちが利用できるだけでなくて、地域の人も利用できるような複合的な施設に将来転換できるような形にしていくことも必要だろうし、保育園も鉄筋で建てたら50年ぐらい使うわけなので、その50年後っていうのは見えないけど、10年、15年先を見て利活用のあり方を考えていくことが必要だろうと思います。
ーー幼児教育や子育てといっても、親や保育園のような当事者だけでなく、みんなで考えていくことが大切なのですね。
保育についてもっとみんなで考える場が必要なのかなと思います。今年(2025年)の5月には、日本保育学会の学会を長野県立大学で開催する予定です。2,000人くらいの研究者が全国から集まります。そこに向けて、これからの保育を考えていくために、「みんなの保育大会議!」というイベントを継続的に開いています。参加者は、保育の現場で働いている人や、県内外の研究者、県立大の卒業生など保育に関わる多様な人たちです。
【参考:2023年8月開催時のチラシ】

ーーイベントではどんなテーマについて話されるのでしょうか?
保育内容や方法、子どもの発達と保育などの基本的な課題はもちろん、保育にまつわるホットトピック、たとえば子育て支援、障がいをもった子どもの保育、愛着や信頼関係が子どもの生育にどう影響するかといったようなことまで、幅広く議論する場になっていますね。
ーー親が共働きをするために保育士を増やすとか、効率化の観点で子育てについて語られることが多いですが、もっと根本の議論が必要なのかもしれませんね。
そう思います。子どもが楽しいのはもちろんのこと、親御さんにも保育士さんにも楽しく子育てをしてほしいっていう思いが僕の根本にはあります。例えば、長野では自然保育に力を入れていますが、キャンプをしたり、焚き火を囲んだり、そういう自然環境が豊かな中で子育てをすると子どもも、大人も楽しいですよね。AIだとかテクノロジーが進展する中で、人間らしさであったり、子どもらしさの見直し、人間らしさへの回帰のようなことも起きているのが今の時代だと思います。
ーー楽しく、幸せな子育てができる地域社会に向けて、みんなで考えていくことの重要性を学ばせていただきました。貴重なお話ありがとうございました!
保育内容や方法、子どもの発達と保育などの基本的な課題はもちろん、保育にまつわるホットトピック、たとえば子育て支援、障がいをもった子どもの保育、愛着や信頼関係が子どもの生育にどう影響するかといったようなことまで、幅広く議論する場になっていますね。
ーー親が共働きをするために保育士を増やすとか、効率化の観点で子育てについて語られることが多いですが、もっと根本の議論が必要なのかもしれませんね。
そう思います。子どもが楽しいのはもちろんのこと、親御さんにも保育士さんにも楽しく子育てをしてほしいっていう思いが僕の根本にはあります。例えば、長野では自然保育に力を入れていますが、キャンプをしたり、焚き火を囲んだり、そういう自然環境が豊かな中で子育てをすると子どもも、大人も楽しいですよね。AIだとかテクノロジーが進展する中で、人間らしさであったり、子どもらしさの見直し、人間らしさへの回帰のようなことも起きているのが今の時代だと思います。
ーー楽しく、幸せな子育てができる地域社会に向けて、みんなで考えていくことの重要性を学ばせていただきました。貴重なお話ありがとうございました!