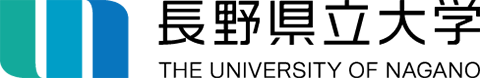これからの公益事業に求められるのは「効率性」と「納得性」の両立? インフラビジネスと研究、行き来した穴山教授が考える公益論 グローバルマネジメント学部長 穴山 悌三 教授
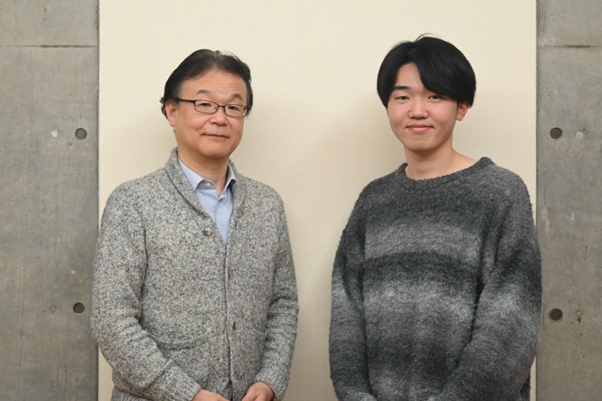
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
長野県立大学が目指すソーシャルイノベーションのためには、理論と実践の両方が欠かせません。そしてこの大学には、地域の中に溶け込んでいくフィールドリサーチとそこから得た知見を地域に還元していく実践の両方に取り組む個性豊かな教員たちが数多くいます。
その一方で、大学の教員がどんなことを考え、どんな思いで研究に取り組んでいるのかが見えづらいのも事実です。
そこで教員たちに最も近い、長野県立大学の学生が、各学部学科、研究科の教員にインタビューを行い、研究されていることや地域との連携についてお話をお伺いしました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
暮らしに欠かせない電気や水道は、これからどう変わっていくのでしょうか?
少子高齢化が進み、公益事業の民営化も進む中で、地方の公益的なサービスの質をどう守るかは大きな課題です。
「効率を追求するならば、人々が都市部へ集約される方向に進むのも一つの合理的な選択肢かもしれません。しかし、すべての人がその選択を望むわけではありません。地方に住み続けたい人々もいる以上、一方的な誘導や強制ではなく、公平な負担を前提とした説明と合意形成が必要になります」
そう語るのは、電力会社での実務経験を経て、産業組織論の視点から公益事業のあり方を研究してきた穴山教授です。少子高齢化や民営化の進展に伴い、地方の公益的なサービスをどう維持していくのかが大きな課題となる中で、「効率性」と「納得性」、「理屈」と「感情」の両方に配慮した公益的なインフラのあり方とはどうあるべきか。穴山教授からお話を伺いました。
インタビュー日:2024年12月17日
聞き手・書き手: 内田 大晴(長野県立大学グローバルマネジメント学部2年 学生コーディネーター)
写真・編集:北埜 航太(長野県立大学 ソーシャル・イノベーション創出センター 地域コーディネーター)
長野県立大学が目指すソーシャルイノベーションのためには、理論と実践の両方が欠かせません。そしてこの大学には、地域の中に溶け込んでいくフィールドリサーチとそこから得た知見を地域に還元していく実践の両方に取り組む個性豊かな教員たちが数多くいます。
その一方で、大学の教員がどんなことを考え、どんな思いで研究に取り組んでいるのかが見えづらいのも事実です。
そこで教員たちに最も近い、長野県立大学の学生が、各学部学科、研究科の教員にインタビューを行い、研究されていることや地域との連携についてお話をお伺いしました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
暮らしに欠かせない電気や水道は、これからどう変わっていくのでしょうか?
少子高齢化が進み、公益事業の民営化も進む中で、地方の公益的なサービスの質をどう守るかは大きな課題です。
「効率を追求するならば、人々が都市部へ集約される方向に進むのも一つの合理的な選択肢かもしれません。しかし、すべての人がその選択を望むわけではありません。地方に住み続けたい人々もいる以上、一方的な誘導や強制ではなく、公平な負担を前提とした説明と合意形成が必要になります」
そう語るのは、電力会社での実務経験を経て、産業組織論の視点から公益事業のあり方を研究してきた穴山教授です。少子高齢化や民営化の進展に伴い、地方の公益的なサービスをどう維持していくのかが大きな課題となる中で、「効率性」と「納得性」、「理屈」と「感情」の両方に配慮した公益的なインフラのあり方とはどうあるべきか。穴山教授からお話を伺いました。
インタビュー日:2024年12月17日
聞き手・書き手: 内田 大晴(長野県立大学グローバルマネジメント学部2年 学生コーディネーター)
写真・編集:北埜 航太(長野県立大学 ソーシャル・イノベーション創出センター 地域コーディネーター)
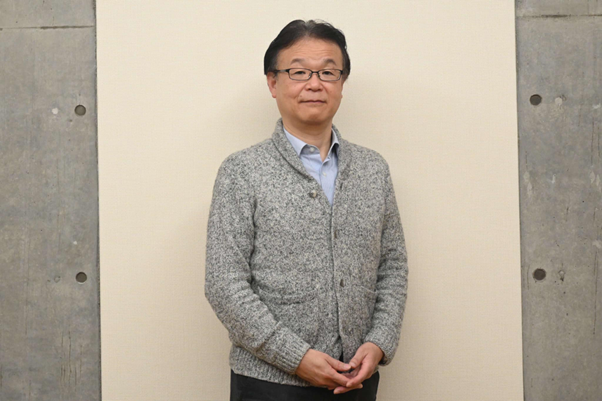
プロフィール:1987年東京電力入社。企画部、電気事業連合会企画部、学習院大学経済学部特別客員教授などを経て、2019年より長野県立大学グローバルマネジメント学部教授。著書に「電力産業の経済学」(2005年、NTT出版)「公益事業の変容 持続可能性を超えて」(共著、2020年、関西学院大学出版会)など。
規制から自由化へ、電力会社の変革に貢献したかった
ーーまず最初に穴山教授の専門分野を教えてください。
私は産業組織論を専門とし、特に公益事業や規制産業の研究を行っています。産業組織論を専門とする恩師に学部時代のゼミでも大学院でもご指導していただいて現在に至ります。
ーー産業組織論とは具体的にどういう学問なのでしょうか?
伝統的な産業組織論は、アメリカなどで生じた世界大恐慌などを背景に発展しました。当時、大企業が市場支配力を持ちすぎることで市場に悪影響を与えるのではないか、という問題意識がありました。競争政策の視点から、市場の集中度や企業行動、パフォーマンスの関連性などについて分析することが、この分野の基本的な考え方でした。
具体的には、ある産業について、その産業の市場構造がどうなっていて、そこで例えば製品差別化・広告宣伝活動・プライシングがどのように行われて、その結果として市場成果がどのようになっているかを分析します。その対象が規制産業になれば当然ながらその規制の仕方をどのようにするんだっていう領域になりますし、競争というところでいけば公正取引委員会のような競争政策となります。
私の場合、大学で産業組織論を学んだあと、電力会社に所属していたので、電気事業の規制改革のあり方とか、料金設定のあり方といったところが自分の専門でもあり、実学的なところがバックボーンです。
私は産業組織論を専門とし、特に公益事業や規制産業の研究を行っています。産業組織論を専門とする恩師に学部時代のゼミでも大学院でもご指導していただいて現在に至ります。
ーー産業組織論とは具体的にどういう学問なのでしょうか?
伝統的な産業組織論は、アメリカなどで生じた世界大恐慌などを背景に発展しました。当時、大企業が市場支配力を持ちすぎることで市場に悪影響を与えるのではないか、という問題意識がありました。競争政策の視点から、市場の集中度や企業行動、パフォーマンスの関連性などについて分析することが、この分野の基本的な考え方でした。
具体的には、ある産業について、その産業の市場構造がどうなっていて、そこで例えば製品差別化・広告宣伝活動・プライシングがどのように行われて、その結果として市場成果がどのようになっているかを分析します。その対象が規制産業になれば当然ながらその規制の仕方をどのようにするんだっていう領域になりますし、競争というところでいけば公正取引委員会のような競争政策となります。
私の場合、大学で産業組織論を学んだあと、電力会社に所属していたので、電気事業の規制改革のあり方とか、料金設定のあり方といったところが自分の専門でもあり、実学的なところがバックボーンです。

——公益事業のあり方についての問題意識は、学生時代からお持ちだったのでしょうか?
そうですね。規制改革について学んできたっていう話をしましたけど、私が大学卒業したのは1987年でちょうどその頃は日本電信電話公社が民営化してNTTになったり、あるいはJRが分割民営化されたり、金融は金融自由化で垣根が壊れて銀行同士の合併が起こったりっていうようなことが、いろんな分野で起きてたんですよ。
当時、産業組織論の界隈ではかなり今までと変わるだろうということは予見されていました。そこで、今までと変わるときにこそ自分が参謀として何かしらの役割を果たせたら良いなと願っていました。
ーー数ある公益事業のなかでも電力業界を選んだのはなぜですか
当時私の就職した電力会社は、大体日本の3分の1の電力需要をカバーするほど大きな会社でした。そうするとそれ以上大きくなるというよりは今後競争自由化が進むと儲けるところを食われていくことになる。そういう苦しい状況になった時に、いかにしてその苦境を超えていけるのか、知恵や工夫でそれを支える参謀のような役割を果たしたいというところにロマンを感じで入社しました。
ーー参謀にロマンを感じたのですね
はい。実は三国志の諸葛孔明が好きだったんです。国の現状を踏まえて弱点を何とかカバーして強みを最大限に活かす、そういう姿勢にロマンを感じたんです。若気の至りですが、就活の際には「今後傾いてゆくかもしれないこの業界において、微力ながらに少しでも支える存在になりたい」と志望動機を語りました。

町田営業所時代——リアルな現場の洗礼
——入社後、実際の仕事はどんなものでしたか?
最初の配属は東京の町田営業所でした。主な業務は、引っ越しに伴う電気契約の手続き、電柱移設の相談、苦情対応など、多岐にわたりました。電気料金の収受窓口の担当などもしていて、様々な理由でお支払いが困難なお客さまの対応などもしてきました。それまでの自分の人生とは異なる環境や価値観などに接することで、世間を広く知ることができたように思います。
また、電柱移設の仕事などでは、期限や費用負担などについて立場ごとに主張も大きく異なるので、自分への苦情や叱られることも多い仕事で、色々鍛えられました。
ーーそのような現場経験をへて、その後は本店の企画部にいかれたのですね。
そうですね。現場で直接お客さまと接したからこそ、データだけでは見えないリアルな課題を知ることができました。戦略を立てたり指示を出すだけでは見えないものがあることを現場から学ばせてもらえたんだと思います。こうした新入社員の限られた時期の経験であっても、現在の仕事につながることはあります。仕事において現場の声はとても大切なんだと思います。
最初の配属は東京の町田営業所でした。主な業務は、引っ越しに伴う電気契約の手続き、電柱移設の相談、苦情対応など、多岐にわたりました。電気料金の収受窓口の担当などもしていて、様々な理由でお支払いが困難なお客さまの対応などもしてきました。それまでの自分の人生とは異なる環境や価値観などに接することで、世間を広く知ることができたように思います。
また、電柱移設の仕事などでは、期限や費用負担などについて立場ごとに主張も大きく異なるので、自分への苦情や叱られることも多い仕事で、色々鍛えられました。
ーーそのような現場経験をへて、その後は本店の企画部にいかれたのですね。
そうですね。現場で直接お客さまと接したからこそ、データだけでは見えないリアルな課題を知ることができました。戦略を立てたり指示を出すだけでは見えないものがあることを現場から学ばせてもらえたんだと思います。こうした新入社員の限られた時期の経験であっても、現在の仕事につながることはあります。仕事において現場の声はとても大切なんだと思います。
大学教員への転身—効率性と納得性を両立した公益事業の未来を目指す
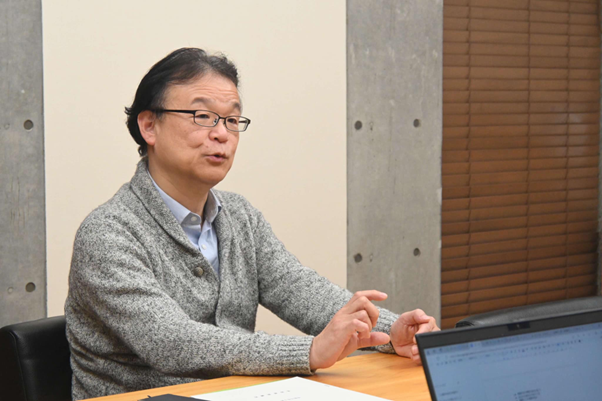
ーー穴山教授は、これまでの経験を踏まえ、今後果たしたい役割や取り組みたいことはありますか?
人口減少が進む社会では、公益的なサービスの維持がますます難しくなります。これまでの規制改革は「自由化による効率化」を特に重視して進められてきました。しかし近年、自由な市場原理に任せるだけでは、社会全体にとって望ましい結果にならない可能性があることが見え、問題視されるようになってきました。そうした流れの中でいまは環境なども同時に重視されていますが、今後はさらに公益性をどうやって維持していけばいいか、例えばそのための新しい料金システムなどへ切り替えていく必要があると考えています。
ーー自由な市場原理に任せるだけでは、社会全体にとって望ましい結果にならない?
はい。効率を追求するならば、人々が都市部へ集約される方向に進むのも一つの合理的な選択肢かもしれません。しかし、すべての人がその選択を望むわけではありません。地方に住み続けたい人々もいる以上、一方的な誘導や強制ではなく、公平な負担を前提とした説明と合意形成が必要になります。具体的には、「地方で暮らし続けるためには、これだけの費用がかかる」という情報を透明に示し、その上で本人が納得できる形で意思決定できる仕組みを整えることが重要です。単に経済合理性だけを追求するのではなく、多様な価値観を尊重しながら、持続可能な社会インフラのあり方を模索していきたいと考えています。
ーーインフラは公益性が高いからこそ理屈だけでなく、納得性も大切にしなければいけないのですね。例えば、合理性と納得性の両方を重視したインフラ事例などはありますか?
小布施町の水道料金制度の検討会で座長を務めています。水道は誰しもにとって必要な物である一方、このままでは水道インフラを維持するために多額のお金が必要なので、適切な料金体系の構築が急務です。そこで今後は公益事業の専門家として、水道料金についての適切な料金体系のあり方を検討して、町民の皆さんに分かりやすく説明する予定です。
また、近年気候変動の流れの中で話題になっている環境分野にも関わっています。環境経済学はミクロ経済学の派生分野の一つとして、私の専門領域と親和性があります。企業に在籍していた頃から、環境政策の立案や説明なども行ってきました。その経験を活かしつつ、長野市の環境審議会会長を務めています。この審議会では環境施策に関する基本計画の策定や毎年の取り組みのフォローアップなどを行います。また、飯綱町の地球温暖化対策の区域政策編の実行計画の取りまとめにも関与しました。
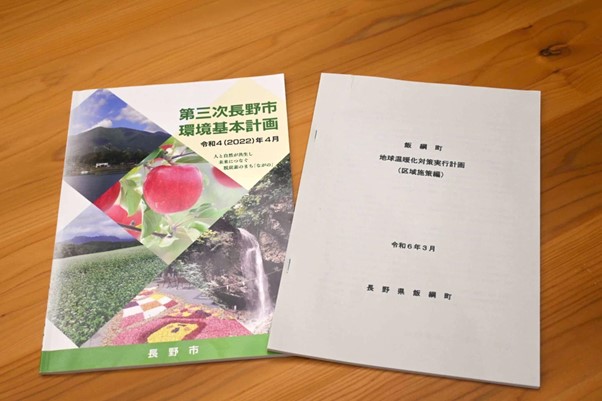
さらに、エネルギー政策にも関心を持ち、地域の脱炭素化に向けた取り組みを支援しています。最近では、長野県立大学ソーシャル・イノベーション創出センター(CSI)の依頼を受け、北信地域の3市(長野市、須坂市、中野市)の市議会議員向けにエネルギーと環境に関する講演を行いました。この講演とその後の情報交換会では、地方自治体がエネルギー政策を推進する上での課題と解決策なども議論され、私もいい勉強の機会となりました。
ーー最後に今後の展望を教えてください
公益的なサービスの持続可能性を高めるためには、「効率性」と「納得性」の両立が求められます。どんなに良い仕組みでも、現場でうまく機能しなければ意味がないので、単にコスト削減を追求するのではなく、住民が納得できる仕組みを構築することが重要です。これからも、電力会社などでの社会人経験と研究活動を通じて学んだ「納得性」や「効率性」の探究を続けて、地域の方々とともに、持続可能な公益事業のあり方を探っていきたいと考えています。
ーー本日は貴重なお話をありがとうございました。「納得性」と「効率性」、時に相反するこの二つを両立させるためには、現場のリアルな課題と経営的な視点を持ちながら、それをアカデミックなエビデンスで支えていくことが大切なのだと感じました。
ーー最後に今後の展望を教えてください
公益的なサービスの持続可能性を高めるためには、「効率性」と「納得性」の両立が求められます。どんなに良い仕組みでも、現場でうまく機能しなければ意味がないので、単にコスト削減を追求するのではなく、住民が納得できる仕組みを構築することが重要です。これからも、電力会社などでの社会人経験と研究活動を通じて学んだ「納得性」や「効率性」の探究を続けて、地域の方々とともに、持続可能な公益事業のあり方を探っていきたいと考えています。
ーー本日は貴重なお話をありがとうございました。「納得性」と「効率性」、時に相反するこの二つを両立させるためには、現場のリアルな課題と経営的な視点を持ちながら、それをアカデミックなエビデンスで支えていくことが大切なのだと感じました。